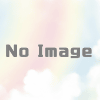調理師 過去問 2017年度版 part2 11~20
問題11
「 日本食品標準成分表2015年版( 七訂 )」に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.収載食品の食品群は、6群に分類されている。
2.廃棄部を含めた原材料 100g中に含まれる、標準的な成分値を収載している。
3.エネルギー量の算出は、アトウォーター係数が統一的に用いられている。
4.食物繊維量については、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維及びその合計の総量で示されている。
正解→ 4
解説
1.
× 「 日本食品標準成分表2015年版( 七訂 )」では、食品が18群に分けられています。
ちなみに、6群に分類されているのは「食事バランスガイド」です。
2.
× 可食部(実際に食べられる部分)100g中に含まれる成分を収載しています。
3.
× 日本食品標準成分表2015年版( 七訂 )において、アトウォーター係数は部分的に使われています。
よって、選択肢中の「統一的に」という記述に合致しないため不適当です。
4.
○ 正解です。日本食品標準成分表2015年版( 七訂 )では、食物繊維の項で水溶性食物繊維と
不溶性食物繊維が分けられています。
問題12
穀類とその加工品の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
1.
うるち米 ── ライスペーパー2.もち米 ── ビーフン
3.小麦 ── 押し麦
4.ライ麦 ── オートミール
正解→ 1
解説
1.
《 穀類 》うるち米 ── ライスペーパーが正解です。
ライスペーパーは、うるち米をくだいて乳液状になったものを薄いシート状にして、乾燥させた加工食品です。
主に、生春巻きに使います。
うるち米から作られる加工品には、せんべいやビーフン、フォーなどがあります。
2.
× ビーフンは、もち米ではなく「うるち米」から作られます。
3.
× 押し麦は、小麦ではなく「大麦」「ライ麦」などから加工されるのが一般的です。
押し麦は、蒸してから平べったく押しつぶして乾燥させたものです。
4.
× オートミールの原料は、ライ麦ではなくエン麦です。
オートミールはエン麦をすりつぶしたものです。
問題13
大豆に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.たんぱく質の主成分は、アルブミンである。
2.制限アミノ酸は、トリプトファンである。
3.含有脂肪の構成脂肪酸としては、リノール酸が最も多い。
4.起泡性成分として、イソフラボンを含む。
正解→ 3
解説
3.
含有脂肪の構成脂肪酸としては、リノール酸が最も多い。
が正解です。
脂肪酸は脂肪を構成する成分のこと。
リノール酸は、コーン油、麺実油、大豆油などの植物油に広く含まれている脂肪酸です。
大豆は、オレイン酸やαリノレン酸などの脂肪酸を多く含み、リノール酸が最も多く含まれています。
1.
× 大豆のたんぱく質の主成分は、アルブミンではなく「グリシニン」です。
2.
× 大豆の制御アミノ酸はトリプトファンではなく「メチオニン」です。
制御アミノ酸とは「アミノ酸スコア」が100以下のアミノ酸こと。
アミノ酸スコアは、アミノ酸の基準値に対してどれくらいの割合でアミノ酸が含まれているかを表す指標です。
(100に近いほどアミノ酸のバランスが良い、良質のたんぱく質ということになります。)
4.
× 大豆に含まれる起泡性成分は、イソフラボンではなく「サポニン」です。
問題14
夏が旬である野菜として、正しいものを一つ選びなさい。
1.長ねぎ
2.大根
3.にんじん
4.きゅうり
正解→ 4
解説
4.
きゅうり が正解です。
きゅうりの旬は6~9月。夏野菜の定番といえるでしょう。
そのことをしっかり覚えていれば、迷わず解ける問題かと思います。
夏が旬の野菜には、ピーマン、おくら、なす、枝豆などがあります。
1.
× 長ねぎの旬は冬(11~2月ごろ)です。
2.
× 大根の旬は、冬(11~2月ごろ)です。
3.
× 人参の旬は、秋(9~11ごろ)です。
通年出まわっている野菜も多いのですが、それぞれに旬があるので、野菜の旬は覚えておきましょう。
問題15
発酵食品とその製造に関与する二種類の微生物の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
1.
ワイン ――― かび・酵母2.かつお節 ―― かび・乳酸菌
3.漬物 ―――― 乳酸菌・酵母
4.清酒 ―――― 乳酸菌・かび
正解→ 3
解説
1.
× ワインは、潰したぶどうに含まれる糖を酵母が発酵させることによって作られます。
基本的にワインの中にカビは発生してはならず、仮にワイン中にカビなどが発生した場合、
香りや味が劣化するため、保存状態には気を遣う必要があります。
2.
× かつお節はカビをあえて発生させることによって、乾燥を促進させます。
また、表面を良いカビで覆うことにより、他の有害菌の付着を防ぐことができます。
3.
○ 漬物の中でも有名なのが「ぬか漬け」です。
「ぬか漬け」は乳酸菌発酵させたぬか床に野菜を漬け込んだ漬物を指します。
乳酸菌と、加えられる塩によって腐敗菌は抑制され、年月とともに独特の風味がつくのが特徴です。
4.
× 清酒は酵母によって発酵します。
原料である米のでんぷんを糖に分解し、アルコール発酵させます。
問題16
機能性表示食品に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.疾病の予防を目的としている。
2.食品の機能性や安全性について、事業者の責任において表示している。
3.販売に当たり、消費者庁長官の許可を必要としている。
4.特別用途食品の一つとして、位置付けられている。
正解→ 2
解説
2.食品の機能性や安全性について、事業者の責任において表示している。
が正解です。
「機能性表示食品」は、科学的根拠をもとに、商品パッケージに安全性や機能性を表示し、事業者の責任で
消費者庁に届け出がされている食品のことです。
特定保健用食品(トクホ)とは異なります。
特定保健用食品は、科学的根拠に基づく機能性や安全性が、国の審査を通過しており、消費者庁長官に、
効果をうたって販売することが許可されているものです。
1.
× 機能性表示食品は、医薬品ではないので、病気を予防・治療する目的で販売・利用することができません。
3.
× まぎらわしいのですが、機能性表示食品は、消費者庁へ届け出されるだけで「消費者長官」から個別の
許可は受けていません。
消費者長官の許可が必要なものは、特定保健用食品(トクホ)です。
4.
× 機能性表示食品は「特別用途食品」ではありません。
特別用途食品は、病人、乳児、幼児、妊産婦など健康の回復・保持など特別な用途に使われる食品です。
特別用途食品には、えん下困難者用食品、乳児用調製粉乳、アレルゲン除去食品などがあります。
問題17
食品・食事と体内の構成成分に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.食品成分による生活習慣病のリスク減少などの効果を、食品の二次機能という。
2.食事と体内の糖質、脂質、たんぱく質の存在比率は、ほぼ等しい。
3.食事から摂取した糖質は、体内で他の構成成分に転換されない。
4.体内の構成成分は、食事から摂取した栄養素によって常に入れ替わっている。
正解→ 4
解説
1.
× 食品成分による生活習慣病リスク減少の効果は、1次機能ではなく3次機能です。
食品三機能を覚えておきましょう。
1次機能…生命維持機能
2次機能…おいしさや腐敗を感じる機能
3次機能…生体防御、老化制御、疾病防止などの生体調節機能
2.
× 食事の糖質、脂質、たんぱく質の存在比率は体内と同じになるとは言い切れません。
3.
× 食事から摂取された糖質は、体内で分解されてグリコーゲンや脂肪などに転換されていきます。
4.
○ 正解です。摂取した栄養によって新陳代謝が起こり、私たちの細胞は入れ替わり続けています。
問題18
脂肪酸に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.パルミチン酸は、n-3系脂肪酸である。
2.リノール酸は、必須脂肪酸である。
3.エイコサペンタエン酸( EPA )は、n-6系脂肪酸である。
4.オレイン酸は、飽和脂肪酸である。
正解→ 2
解説
1.
× パルチミン酸はn-3系脂肪酸ではなく、飽和脂肪酸です。
2.
○ 必須脂肪酸はしっかりと覚えておきましょう。
n-3系脂肪酸…α?リノレン酸、DHA、EPA
n-6系脂肪酸…リノール酸、アラキドン酸
3.
× エイコサペンタエン酸(EPA)はn-3系脂肪酸です。
4.
× オレイン酸はオリーブオイルなどに含まれる「不飽和脂肪酸」です。
問題19
鉄に関する記述について、誤っているものを一つ選びなさい。
1.ヘム鉄は、植物性食品に含まれる鉄である。
2.体内に存在する鉄の多くは、ヘモグロビン中に存在する。
3.消化管における鉄の吸収率は、ビタミンCによって高くなる。
4.鉄の摂取不足は、貧血の原因となる。
正解→ 1
解説
1.
ヘム鉄は、植物性食品に含まれる鉄である。
を選択するのが正解です。
鉄には吸収されやすい「ヘム鉄」と吸収されにくい「非ヘム鉄」があり、貧血を効率よく予防・改善するには、
ヘム鉄を摂取することが勧められます。
ヘム鉄は、動物性食品に含まれ、非ヘム鉄は植物性食品に含まれています。つまり「ヘム鉄は、植物性食品に
含まれる鉄である。」は誤りです。
2.
× 体内に存在する鉄の7割が血液中のヘモグロビンに存在しており、設問の文章は正しいです。
3.
× 鉄はビタミンCと一緒に摂取することで腸からの吸収率が高まるので、設問の文章は正しいです。
4.
× 鉄は赤血球を構成するヘモグロビンの材料です。
鉄が不足すると、酸素を運搬するヘモグロビンが不足し、酸欠による倦怠感や動悸などが起こりやすく
なります。これを「鉄欠乏性貧血」といいます。設問の文章のとおりです。
問題20
摂食の調節に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
1.においは、摂食行動や食品の嗜好に影響を与えない。
2.食欲は、脳でコントロールされている。
3.胃に食物が満たされると、摂食中枢が刺激される。
4.糖質は、脂質やたんぱく質より満腹感を持続させる。
正解→ 2
解説
2.食欲は、脳でコントロールされている。
が正解です。
食欲は、活動によって体のエネルギーを消費し、エネルギーの補充が必要になった時に起こる、本能的な
欲求です。
食欲を調節しているのは、脳の視床下部にある「食欲中枢」です。
食欲中枢には空腹を感じさせ、「食べたい」という欲求を起こす「摂食中枢」と、満腹を感じさせ食欲を
抑える「満腹中枢」があります。
1.
× 一種の香りは、胃液の分泌を高めて食欲を亢進させます。
逆に、不快なにおいには食欲を減退させる作用があります。
3.
× 胃に食物が満たされると、満腹中枢が刺激されて「おなかいっぱい」と感じます。
4.
× 満腹感を持続させやすいのは、消化に時間がかかり、胃に停滞する時間が長いたんぱく質や脂質です。
糖質は消化されやすく胃に停滞する時間が短い分、たんぱく質や脂質よりも満腹感は持続しにくいのです。